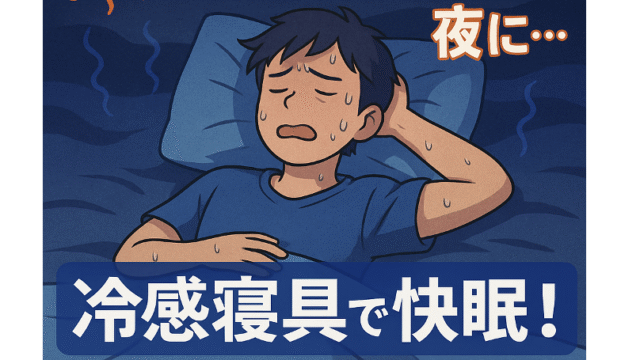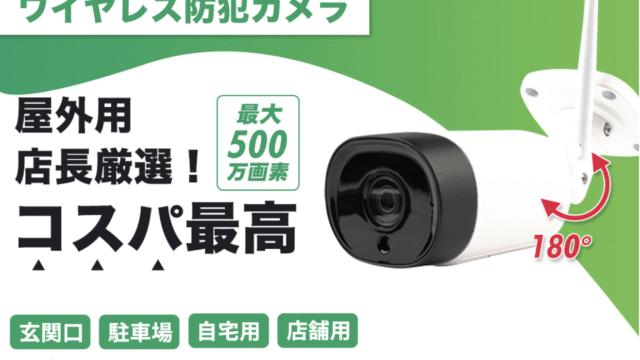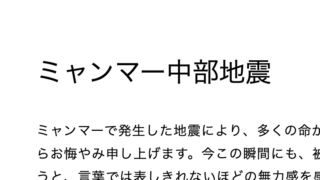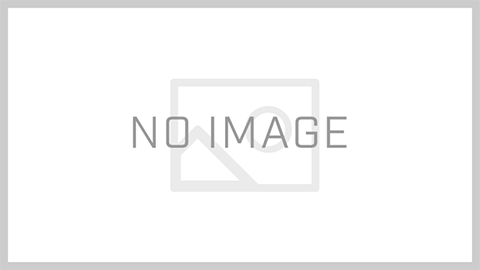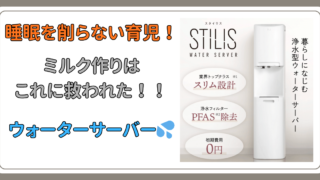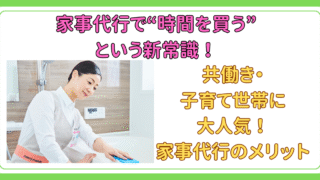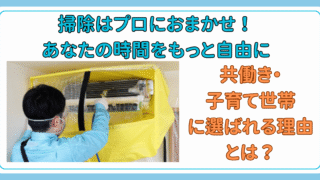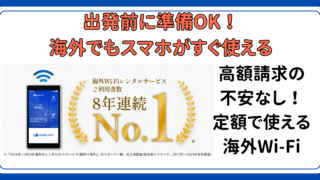地震が発生したら、皆さんは冷静に対応できますか?
火元やガラスから離れたり、机の下などに隠れて落下物から身を守る行動を取ることができるでしょうか。
昨今の頻発する地震により、発災中にどうすれば良いかはテレビやSNSでも多く発信されているので、周知されているようです。
ですが、「地震の揺れが収まるまで自分の命を守りきることができればもう大丈夫」とはいきません。
地震は「発災中」と「発災後の二次災害」の両方に気をつけなければなりません。
二次災害として最もよく知られているのは津波でしょう。
地震直後は動揺して冷静に次の行動を取ることが困難になります。
他にも様々な二次災害があるので、事前に知っておくことが生死の分け目になるのです。
今回は、注意すべき二次災害について紹介します。
1:火災
地震による家具の転倒や電気系統の損傷が原因で発生することがあります。
また、戸建て住宅が密集した地域では火災旋風に気をつけましょう。
火災旋風とは、火災時に発生する竜巻状の渦で、大規模な火災の際に起こる危険な現象です。
猛烈な風により人や物を吹き飛ばし、死傷者を出す可能性があり、火の粉を広範囲に飛ばし、急速な延焼拡大をもたらします。
大気中の渦が火災によって一カ所に集まり、回転が強くなって発生すると考えられています。
2:津波
海岸付近では地震発生後数分から数十分で押し寄せる可能性があります。
津波が発生したら、自分がいる地域にどれぐらいの時間で到達するかの予想時間を事前に調べておくと落ち着いて行動できるでしょう。
3:余震
大型地震の後には複数回発生する可能性があり、場合によっては本震と同等もしくはそれ以上の規模になることもあります。
家屋倒壊などの新たな被害をもたらす恐れがあります。
4:ライフラインの断絶
電気、ガス、水道などの供給が停止する可能性があります。
防災備蓄にこららをカバーできるように、ポータブル電源、カセットコンロ、備蓄水などを用意しておくと良いでしょう。
5:通信の断絶
電波の乱れや電気の寸断により、通信機器が使用できなくなる可能性があります。
事前に家族で話し合い、連絡が取れなくなっても会えるよう、避難所のどこで集合するかなど決めておくといいでしょう。
6:地割れ・液状化現象
地面に亀裂が入ったり、地盤が液体状になったりして、建物の傾斜や沈下、マンホールの浮き上がりなどが起こる可能性があります。
7:がけ崩れ・土砂災害
地震の揺れにより斜面が崩壊する危険性があります。
豪雨などの際にも注意が必要で、地鳴りや土の匂いがすると、その前兆とも言われています。
家の裏に山がある場合は、地滑りや土石流などの恐れがあるので、揺れを感じたら避難をしましょう。
8:複合災害
例えば、新潟県中越地震では地震後の豪雪により、雪崩被害の拡大や道路復旧工事の遅れなどが発生しました。その地域の特有の気象条件などが合わさり、被害が拡大することも考えられます。
防災備蓄などには地域によって必要な備えを加えることも大切です。
積雪の多い地域では暖をとることができる石油ストーブやカイロを多めに、
夏の暑さが厳しい地域では、熱中症対策に塩分タブレットや化学反応で冷却できるアイスバッグを用意するなど、オリジナルのカスタマイズをしましょう。

まとめ
今回は、地震直後に発生する可能性のある二次災害について紹介しました。地震直後はそれだけ冷静にかつ迅速に行動ができるかが生死の分け目になります。
以前の記事でも紹介しましたが、迅速に走って逃げるために役立つのが防災靴、踏み抜き防止インソールです。また、夜間の避難にはヘッドライトが必須です。これらは常に寝室には備えておきましょう。それぞれの二次災害を防ぐための避難経路や避難先を事前確認することが重要です。
引用:
上越市 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kikikanri/dosyachuui.html
内閣府 https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h27/79/special_02.html
LOTTE https://www.lotte.co.jp/products/brand/hiyaron